|
前2200ころ
|
バビロニアの数学記録
掛算表 2乗・3乗表,逆数表などを使う。
平方根の近似値として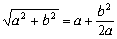 を使
う。(aに対しbが 小さいとき) を使
う。(aに対しbが 小さいとき)
2次方程式を解いた。
|
|
前1650ころ
|
エジプトでアーメスのパピルスが書かれた。
単位分数についての表を用いて計算する。
等差級数,等比級数,比例配分等の問題を含む。
問題の中に未知数を表すことばhauが使われる。(代数のはじめ)
|
|
前600ころ
|
ギリシア;タレス(前640?~546?)エジプトの実用幾何学を導入(論理的な幾何学を始める。
|
|
前540ころ
|
ギリシア;ピタゴラス(前580?〜500?)数を分類,いろいろの比例を考える。
無理数を発見する。
ピタゴラスの定理の発見
|
|
前430ころ
|
ギリシア;ソフィストたちによって幾何学の三大問題が研究される。
|
|
前300ころ
|
ギリシア;ユークリッド「幾何原本」を著わす。
比例論を完成。
最大大公約数を求める互除法を提案。
素数が無限に多いことを証明した。
|
|
前250ころ
|
ギリシア;アルキメデス(前287?〜212)
円周率を計算。
球と円柱との数量関係を発見した。
大きな数の記数法を案出。
積尽法を用いて放物線の面積を明らかにした。積分法の先駆者というべきである。
|
|
前230ころ
|
ギリシア;エラトステネス(前275?〜194)素数を求める「エラトステネスのふるい」の方法を案出した。
|
|
前230ころ
|
ギリシア;アポロニウス(前260?〜200?)「円錐曲線論」を著わす。
ギリシア;ニコマコス「算学入門」を著わす。算術数科書の最初のもの。
|
|
100ころ
|
中国;「九章算術」が完成した。第8章「方程」では,連立一次方程式になる問題を集め,加減法によって解いている。
|
|
125ころ
|
ギリシア;プトレマイオス(トレミー)三角法を研究した。
|
|
300ころ
|
ギリシア;ディオファンタス(330ころ没)「アリスメチカ」を著わす。方程式および不定方程式を取り扱う。方程式を記号で書きあらわした。
|
|
470ころ
|
中国;祖沖之(429〜500)円周率を お よび お よび とする。 とする。
|
|
500ころ
|
中国;「張邱建昇経」に一次の不定方程式となる問題が載せられる。
ローマ;ボエティウス(475?〜524)「算学入門」を著わす。後世まで広く行われた。
|
|
510ころ
|
インド;アリアバタ(476?生)「アリアバティーア」を著わす。連分数によって一次の不定方程式の一般解を得ようとした。
|
|
628ころ
|
インド;ブラマグプク(598生)連立方程式のいくつかの未知数に色の名をつけ,その頭文字を記号とした。
二次方程式ax2+bx=cの根を  と した。 と した。
|
|
820ころ
|
アラビア;アル=クワリズミ(850ごろ死)「アルジャブル・ワル・ムカバラ」を著わす。これからalgebra(代
数)の名がで た。
二次方程式を図によって解く。
|
|
876ころ
|
インド;0の記号がはじめて碑文見える。
|
|
1090こ
ろ
|
アラビア;オマル=カイヤム(1038?〜1123?)円錐曲線の交点として三次方程式を解いた。
|
|
1150こ
ろ
|
インド;バスカラ(1114〜1185?)負の数を負債で説明した。
二次方程式に2根を認めた。
 等をしるす。 等をしるす。
|
|
1202
|
イタリア;ピサのレオナルド(フイボナッナ)(l170?〜1250?)
「リベル・アバチ」を著し,インドの記数法とアラビアの数学をヨーロッパに紹介 する。
|
|
1247
|
中国;秦九韶(1198?〜1261?)ホルナーの方法と同じ方法で数字係数の十次方程式まで近似
的に解く。
|
|
1248
|
中国;李治(1192〜1279)「測円海鏡」を著わし,天元術を詳しく記す。算木による代数で
あって,未知数を天元 の一という。
|
|
1261
|
中国;「宋揚輝算法」にパスカルの三角形の図を載せる。
|
|
1449
|
イタリア;ルカス=パチオリ(1445?〜1515?)「ズーマ」を著わして,当時の算術・代数・三角法などの知
識を集成する。複式簿 記の最初の書物。
|
|
1464
|
ドイツ; レギオモンタヌス(1436〜1476)「三角形について」を著わす。三角法だけを書いた最初の書。
|
|
1489
|
ドイツ;ヨハネス=ヴィドマン(1460ころ生)算術書を著わし,過剰・不足を表わす記号として+,一を用いた。
|
|
1505
|
イタリア;シピオ=フェロ(1465?〜1526) の 形の三次方程式の解き方を弟子に教えた。 の 形の三次方程式の解き方を弟子に教えた。
|
|
1525
|
ドイツ;クリズトフ=ルドルフ(1500ごろ生)根号として√を用いた。
|
|
1535
|
イタリア;タルタリア(1506?〜1557)x3=mx+nの形の三次方程式を解
き,数学試合に勝つ。
|
|
1540
|
イギリス;ロバート=レコード(1510?〜1558)の算術書で,加法,滅法の記号として十,−を用いた。
|
|
1541
|
イタリア;タルタリア,三次方程式の一般的な解法を得た。
|
|
1544
|
ドイツ;シェティフェル(1486?〜1567)等差級数の各項と等比級数の各項を対比配列する利益を述べ
る。(a+b)
の18乗以下の展開における二項係数を求めた。
|
|
1545
|
イタリア;カルダノ(1501〜1576)「アルス・マグナ」を著わし,タルタリアの三次方程式の解法
と,自己の弟子フェラリ (1522〜1560?) の四次方程式の解法を載せた。虚根を認めた。
|
|
1557
|
イギリス;ロバート=レコードの代数の書で,等号として=を用いた。
|
|
1572
|
イタリア;ボンベリ,代数の書物を著わし,三次方程式が既約の場合,3実根をもつことを認めた。
|
|
1585
|
(ベルギ一)シモン=ステヴィン(1548〜1620?)「ラ・ディズム」を著し,小数の意味と計算法を説明した。
|
|
1591
|
フランス;フランシス=ヴィエタ(1540〜1603)解析術序論」を著わし,はじめて代数を記号的に取り扱った。既
知数を表わすのに子音 文字を,未知数を表わすのに母音文字を使う。
|
|
1614
|
イギリス;ジョン=ネーピア(1550〜1617)対数についての書物を著わす。
|
|
1617
|
イギリス;ジョン=ネーピア,小数点に.を用いた。
|
|
1624
|
イギリス;へンリ=ブリッグス(1556?〜1630)10を底とする常用対数の表を出版。
|
|
1629
|
フランス;アルべ−ル=ジラール(1590?〜1633)「代数学の新発明」を著わし,方程式の根と係数との関係を証明
した。すべての方程式 はその次数だけの数の根を有することを推論した。
フランス;フェルマー(1601〜1665)関数の極大,極小値を求める方法を発表。極値の付近
で,f(a)=f(a+e),e=0のとき極値を与える。
|
|
1629
|
イタリア;カバリエリ(1598〜1647)不可分法(無限小の法)の原理によって多数の求積の問題を解い
た。微積分学の先駆 者。
イギリス;トマス=ハリオット(1560〜1621)「解析術の実際」で不等号>,<を用いる。方程式の根と係数と
の関係をジラールより 簡単な形で表わす。
|
|
1637
|
イギリス;オートレッド(1574〜1660)乗法の記号として × を用いる。
|
|
1637
|
フランス;デカルト(1596〜1650)「方法序説」の付録として「幾何学」を著わす。解析幾何学のは
じめ。
方程式の記号を改良。現代とおなじくアルファベットのおわりのほうの文字で未知数を,はじめのほうの文字で既知数を表わした。
方程式の根の性質を研 究,いわゆるデカルトの符号の法則を発見。
|
|
1638
|
フランス;デカルト,友人への手紙の中で,曲線と直線との二つの交点が合一する極限の場合として接線を考えた。
|
|
1639
|
フランス;デザルグ(1593〜1662)円錐曲線に関する研究を公にして,射影幾何学をはじめた。
|
|
1640
|
フランス;パスカル(1623〜1662)「円錐曲線論」を出版した。パスカルの定理が含まれる。
|
|
1642
|
フランス;パスカル,はじめて,計算器を作った。
|
|
1644
|
フランス;フェルマー.一般の高次の放物線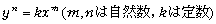 の
求積 に成功。 の
求積 に成功。
|
|
1646
|
イタリア;トリチェリ(1608〜1647)一般の高次の双曲線
xmyn=k(m,nは自然数,kは定数)の求積に成功。
|
|
1651
|
イギリス;ヴィンセント=ウィングの書物に比の記号:が用いられる。
|
|
1654
|
フランス;パスカルとフェルマーの間に往復した手紙によって確率論がはじまった。
フランス;パスカルの「算術三角形」が出版される。いわゆるパスカルの三角形が記される。
|
|
1655
|
イギリス;ジョン=ウォリス(1616〜1703)「無限に関する算術」を著わす。無限大の記号∞をはじめる。
連続の法則を代数に応用, ……
のように分数の分 母を負数指数として表わした。 ……
のように分数の分 母を負数指数として表わした。
|
|
1660こ
ろ
|
イギリス;バーロウ(1630〜1677)変数値の微小変化e,これに対する関数の変化αに対し, から接線を引くことを考える。微分と積分と逆の関係にあることを認めた。 から接線を引くことを考える。微分と積分と逆の関係にあることを認めた。
|
|
1665〜66
|
イギリス;アイザック=ニュートン(1642〜1727)微積分学を発見,流率法とよぶ。
現在の変数や関数を流量と名づける。関数のかわっていく比率すなわち現在の導関数を流率という。流量x,yの流率を で表わす。 で表わす。
流率法に関する書物は1671に書かれ1736に出版。
|
|
1674
|
日本;関孝和(1642?〜1708)筆算による代数を発明,「発徴算法」を著わす。
筆算による代数は後に点ざん術とよばれる。
|
|
1673〜77
|
ドイツ;ライプニッツ(1646〜1716)微積分学を発見。微分の記号としてdxおよびdyを,
積分の記号として を用いた。 を用いた。
1684お
よび1686に印刷物の上に発表。
|
|
1676
|
イギリス;ニュートン,友人への手紙中に,二項定理を説明した。
|
|
1683
|
日本;関孝和,二つ以上の方程式から未知数を消去するために行列式を発明,「解伏題之法」を著わす。
|
|
1692
|
ドイツ;ライプニッツ,座標という語を用いる。
|
|
1693
|
ドイツ;ライプニッツ,友人への手紙の中に行列式を説明した。
|
|
1707
|
イギリス;ド=モアブル(1667〜1754)三角関数に虚数を使用した。
|
|
1715
|
イギリス;テーラー(1685〜1731)
テーラーの級数 …を発表。 …を発表。
|
|
1742
|
イギリス;マクローリン(1698〜1746)
マクローリンの級数 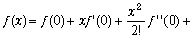 …を発
表。 …を発
表。
|
|
1795
|
ドイツ;ガウス(1777〜1855)最小自乗法を発明する。
フランス;モンジュ(1746〜1818)「画法幾何学」を出版する。
|
|
1795
|
ドイツ;ガウス,複素数を平面上に図示する。
|
|
1798
|
フランス;ラクロア(1765〜1843)標準式
 をしるす。 をしるす。
|
|
1799
|
ドイツ;ガウス,代数学の基本的定理を証明する。方程式は少なくとも一つの根を有する。
|
|
1809
|
(スイス)リュイリエ(1750〜1840)へツセの標準形 xcos
a +ysin a=pを記す。
|
|
1814
|
フランス;セルヴォア,代数学における交換の法則,分配の法則の名をつける。
|
|
1821
|
フランス;コーシー(1789〜1857)「解析教程」を著わし,関数の定義を新しく与える。
「xのきまった値に対し,yのきまった有限の値が対応するとき,yはxの関数で
ある」図によらず現在のような関数の連続性の定義を与える。
|
|
1821
|
ドイツ;クレレ(1780〜1855)直線の方程式 をしるす。 をしるす。
|
|
1822
|
フランス;ポンスレー(1788〜1867)射影幾何学を大成した。
|
|
1825
|
(ハンガリー)ヨハン=ボヤイ(1802〜1860)非ユークリッド幾何を発表。
|
|
1826
|
ロシア;ロバチュウスキー(1793〜1856)非ユークリッド幾何を発表。
(ノルウェー)アーベル(1802〜1829)五次以上の一般方程式は,代数的解法が不能であることを証明し
た。
|
|
1850
|
フランス;マネーム(1831〜1906)現在のような形の計算尺を考案した。
|
|
1854
|
ドイツ;リ−マン(1826〜1866)リ−マン幾何学をはじめる。
|
|
1872
|
ドイツ;クライン(1849〜1925)エルランゲンの目録を発表,幾何学を統一的な方法によって分類
した。
ドイツ;カントール(1845〜1918)集合論をはじめた。
ドイツ;デデキント(1831〜1916)無理数論をはじめた。
|
|
1899
|
ドイツ;ヒルベルト(1862〜1943)「幾何学の基礎」を著わし,公理主義の幾何をはじめた。
|
|
1903
|
イギリス;ラッセル(1872〜 )集合論の背理を指摘。
|
|
1914
|
ドイツ;ハウスドルフ(1868〜1942)位相空間論の研究。
|
|
1922
|
イギリス;フイツシャー(1890〜 )推測統計学の基礎碓立。
|
|
1940〜
|
フランス;ブールバキ派,数学の各分野で活躍。
|